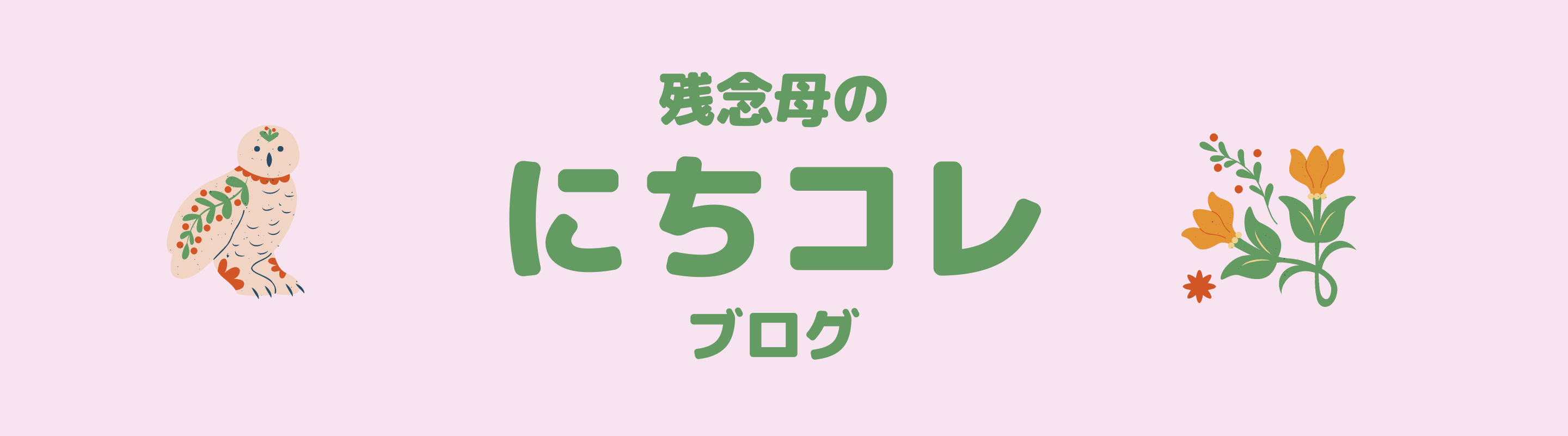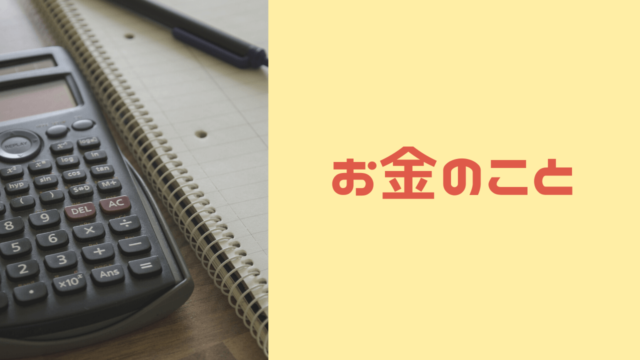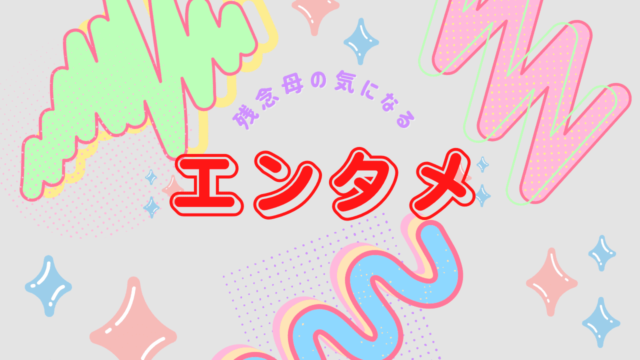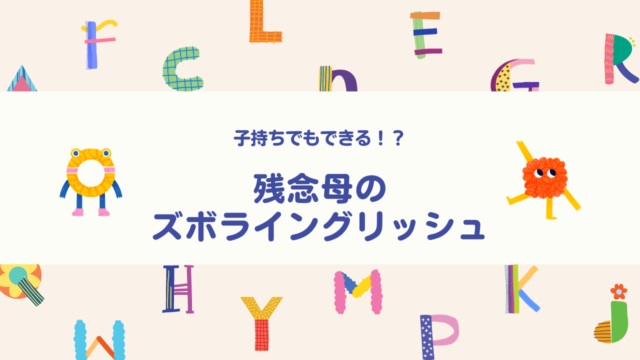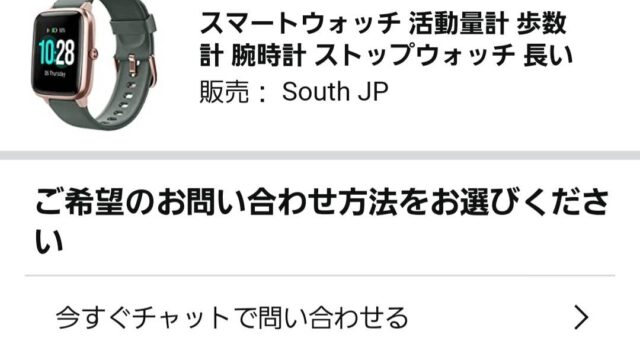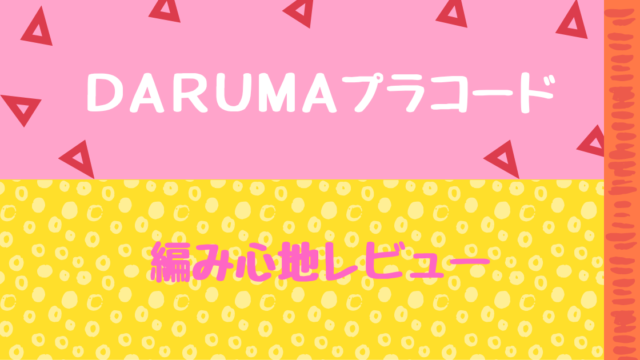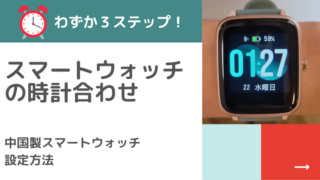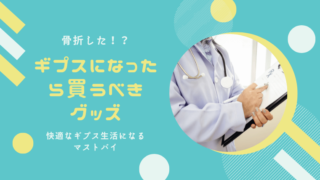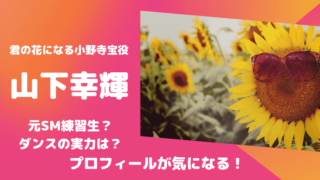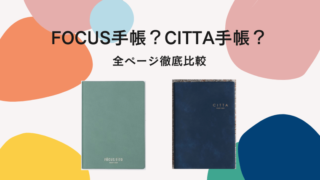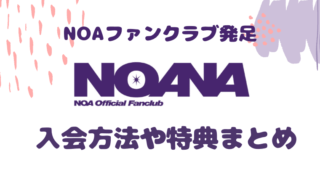我が家には小学生の子がおります。
その小学生が毎日学校へ持っていき、毎日家でも使うアイテム。といえば何でしょう。
そう、それは鉛筆!
毎日毎日削っては持っていき、持って帰っては削る鉛筆。
我が家には短くなった鉛筆(以下チビた鉛筆←なぜか我が家の夫がこう言う)が沢山あります。
ある程度の長さまでは鉛筆ホルダーでカバーすれば使えるのですが、そのうち削ることすら困難になってゆく鉛筆たち。
捨てるには忍びない。かといって使うにも使えない。
そんな鉛筆を救うアイテムがあるのです。
そんな神のようなアイテムの名はTSUNAGO®️
大阪にある中島重久堂という鉛筆削りのメーカーが開発された、短くなった鉛筆たちを繋げて甦らせるという画期的な鉛筆削りなのです!
ん?鉛筆を蘇らせるのに鉛筆削りってどういうこと!?
長くしたいんだか短くしたいんだかどっちだよ!?
と思われた皆さん。
安心してください。つなぎますよ。
というわけで、簡単に説明すると、短くなった鉛筆のお尻の部分に穴を開けて、もう1本の鉛筆の先っちょをぶっ差す!穴を開けてぶっ差す、穴を開けてぶっ差す。
この繰り返しで短くなった鉛筆がまるで使い始めのような長さになるのです。
イメージ的には昔懐かしロケット鉛筆に近いものがあるかも知れません。
ロケット鉛筆も短い芯が繋がって1本の鉛筆になっていますよね。
とはいえ、説明だけではわかりにくいと思うのでここからは実際に穴を開けていきたいと思います!

これがTSUNAGO®️の本体です。
某○天市場で注文したのですが、想像していたサイズよりもかなり小ぶりです。
リラ社の小さい子向けの鉛筆の形をした鉛筆削りよりもほんの少し小さいかなぁというサイズ←ニッチ過ぎてかえってわかりずらい説明🤣
よくあるプラスチックの筒型鉛筆削りと同じような見た目で、下の透明のところに削りカスが溜まって、上の黒い蓋を開けてゴミ箱に捨てられます。

その蓋の部分に注目してみましょう。

団子三兄弟のような赤い○がありますね。
そしてその下には何やらマークが彫られています。

そう、これが鉛筆を繋ぐ画期的な鉛筆削りTSUNAGO®️のメインシステム、3種類の削り機がついているのです。
凸に削る穴と凹に削る穴と凸の削られた面を滑らかに整える穴。
ちびた鉛筆の鉛筆のお尻と先っぽとをこの削り機で加工して繋げていくのですね。
ふむふむ、では早速実践してみましょう!
ご覧ください、我が家のチビた鉛筆達。

これでも減った方なんです。
蓋が閉まらないくらいにパンパンでした。
TSUNAGO®️が我が家に来るまでは。
というわけで早速そうですね、君と君でやってみましょうかね。

説明書を読みながら、、、ふむふむ、まずは1のダイヤルにセットして

お尻を入れる。

時計回りに回す。
むむむ、なんせ短い上に先っぽが手に当たるもんで持ちにくい。
安心してください。想定内ですよ。
と開発者の方の声が聞こえてきそうな事案です。
本体とは別に、丸いパーツが一緒についてきます。
これです。これ。

これをここに刺して。。。

おぉ!!!断然持ちやすい!!そして回しやすい!!!!
なんと痒いところまで手が届く素晴らしいプロダクト!!!
(丸についている赤い棒ははずして置いておきます)
というわけで気を取り直して時計回りに回していきます。
うーん、何だろこの感触。全然削れてる感触がない。
ほんとに削れてる!?
疑いの気持ちのまま一度削るのをやめてみます。

おぉ、わずかに穴が開いています。
説明書によると、この時の穴が芯の中心を射ているのが大事なようです。
確かにここがズレると先っぽを差した時に歪みそうですよね。
というわけで削り続けます。
うーーーーーーん、めんどkusxxxx
これはなかなか時間がかかります。
目安はこの赤い線のところに鉛筆が来るように、とのことです。

んーーーーー流石に飽きてきたなーーーーと思った頃、赤い線に到達!
早速鉛筆を抜いて削った側を見てみる。
芯の粉が溜まっているのでトントンとテッシュに落とす。

ほほぉ。この穴に鉛筆の先っちょを差していくわけですな!
長くなったので続きます→その2へ